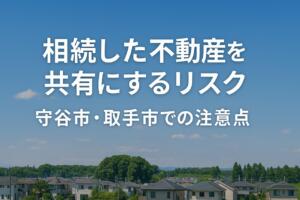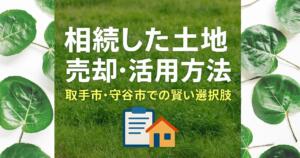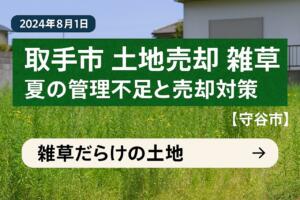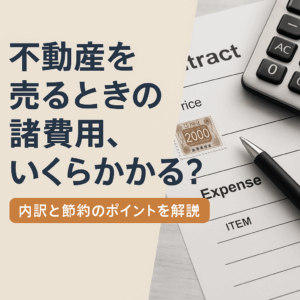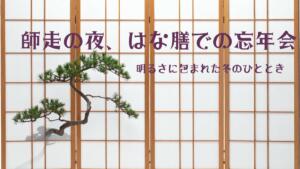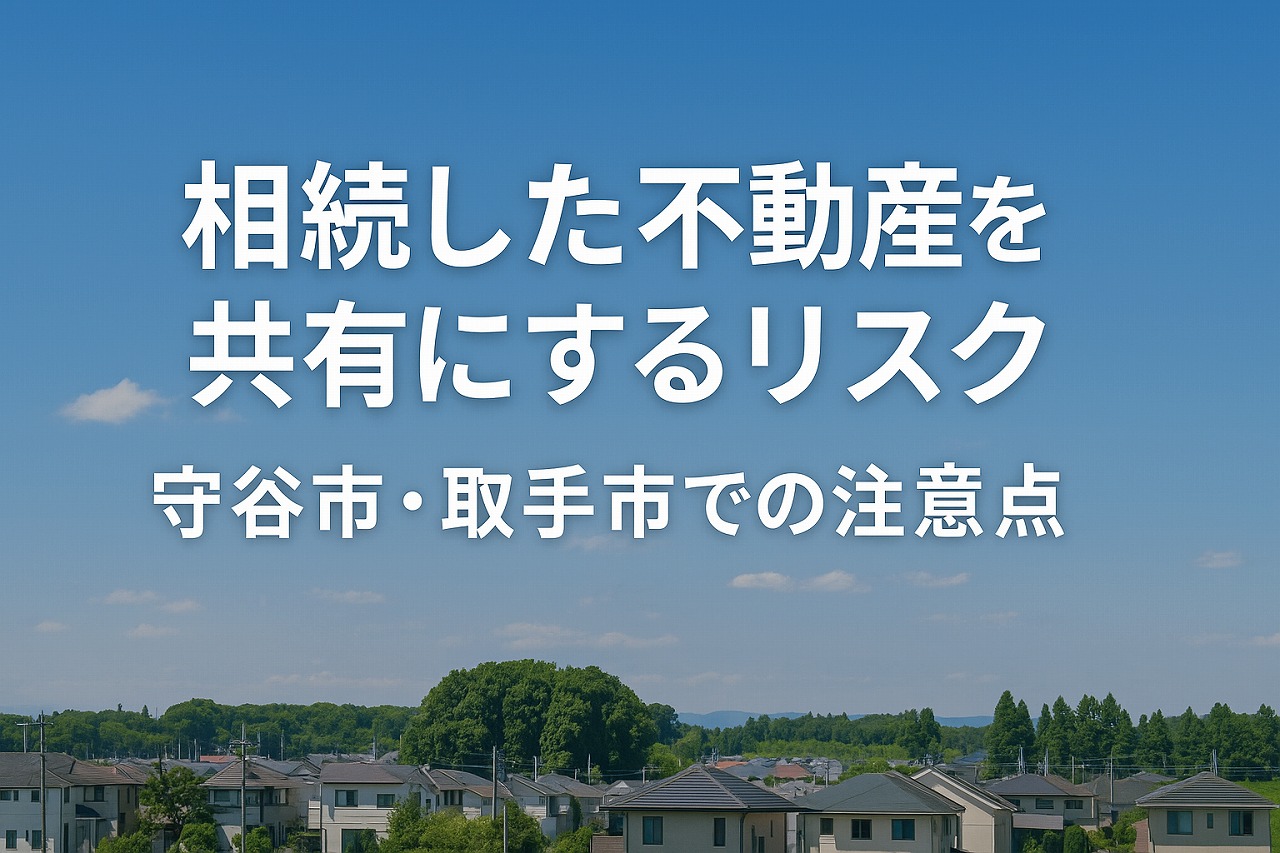はじめに|相続後の「共有」は本当に安全?
相続で不動産を受け継いだとき、「とりあえず兄弟で共有にしておこう」と決めてしまうケースは少なくありません。しかし、この「安易な共有」が将来大きなトラブルの火種になることをご存じでしょうか。特に売却や活用を考えたとき、共有状態は意思決定の大きな障害となります。
この記事では、守谷市・取手市エリアで不動産相続や売却のサポートを行ってきた不動産コンサルティングマスター(資格保有者:羽生 利夫)の視点から、共有のリスクと回避方法、すでに共有になってしまった場合の解決策をやさしく解説します。
1. 共有とは何か|持分の仕組みを理解する
「共有」とは、ひとつの不動産を複数人で所有する状態です。相続の場合、遺産分割協議を行わないまま登記すると、相続人全員が法定相続分の割合で共有することになります。
例えば、相続人が2人で持分が50%ずつの場合、建物を売却するにも、貸すにも、原則として全員の同意が必要です。この同意が得られないと、不動産は事実上「何もできない資産」と化してしまいます。
詳しくは、相続発生後の初動5ステップの記事でも解説しています。
2. 共有の3つの大きなリスク
① 意思決定が困難になる
売却や賃貸など、不動産の活用には原則全員の同意が必要です。1人でも反対すると計画が頓挫します。
② トラブルが長期化する
相続人の数が多くなるほど意見がまとまりにくくなります。将来、相続人の一人が亡くなればさらに相続が発生し、共有者はどんどん増えていきます。
③ 資産価値が下がる可能性
特に市街化調整区域では、利用制限が厳しく買い手が限られるため、市街化区域の不動産と比べて資産価値が低くなる傾向があります。共有状態ではさらに売却が難しくなります。
3. 守谷市・取手市の事例
守谷市のケース
農地を兄弟3人で相続し共有にしたが、うち1人が他県に在住。農地の売却話が持ち上がった際、その1人と連絡が取れず売却が2年以上停滞。
取手市のケース
市街化調整区域の宅地を2人で共有。1人が売却を希望するも、もう1人が「将来子どもが使うかもしれない」と拒否。結局、固定資産税だけが毎年発生。
4. 共有を避けるための方法
① 遺産分割協議で単独所有にする
不動産を1人が相続し、他の相続人には現金や別の資産で調整します。詳しくは、相続発生後の初動5ステップで解説しています。
② 換価分割
不動産を売却し、その売却代金を相続人で分けます。
③ 代償分割
特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払います。
5. 共有になってしまった場合の解決策
① 共有物分割請求
民法に基づき、共有者が共有状態を解消するための法的手続きです。詳しくは、法務省:通常の共有関係の解消方法(共有物分割請求の手続き)をご覧ください。
② 買取交渉
他の共有者に自分の持分を買い取ってもらう、または自分が他の共有者の持分を買い取る方法です。
③ 第三者への売却
持分のみを不動産業者などに売却することも可能ですが、通常は大きく値引きされます。
6. 専門家に相談するメリット
共有解消や相続の調整は法律・税務・不動産の知識が必要です。個人で対応しようとすると時間と労力がかかり、結果的に損をすることもあります。
株式会社たくみ総合企画では、不動産コンサルティングマスター(資格者:羽生 利夫)として、守谷市・取手市エリアの相続不動産の活用・売却をご提案しています。
まとめ
相続不動産を安易に共有にすることは、将来のトラブルの種をまくようなものです。意思決定の遅延、資産価値の低下、固定資産税などの維持費負担——これらのリスクを避けるためには、早めの相談と適切な手続きが不可欠です。
守谷市・取手市で相続不動産をお持ちの方は、ぜひ一度、株式会社たくみ総合企画へご相談ください。